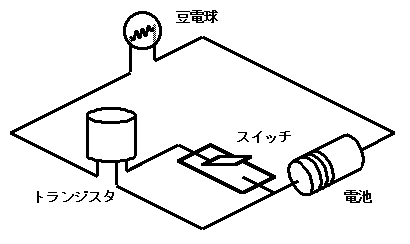
図4(相変わらず汚い図で申し訳ありません。)
(Update '05/07/05)
でも、「トランジスタ」とは何をするものなのでしょうか?
では、下の図をごらんください。
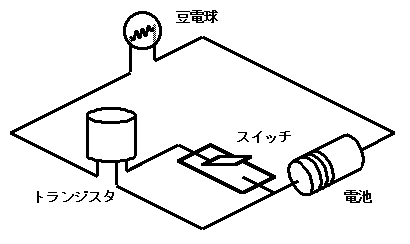
この図は、「豆電球と電池」図1のスイッチのところに、「トランジスタ」が居座った図です。
「トランジスタ」からは足が3本でていて、そのうちの一つにスイッチがついています。
ここで、スイッチを入れると、豆電球が灯ります。スイッチを切ると、豆電球が消えます。
「1章の図と、動作は変わらないじゃん!」と思う方は、すごい記憶力です。
「トランジスタ」の中は、「半導体」と言う石(鉱物)で出来ています。
「導体」と言えば、電気を通すものですが、「半導体」は、「導体」の半分なのです・・・
と言っても分からないので、詳しく説明します。
半導体は、普段は電気を通しません。
三方のうちの一方に電気が流れると、残りの二方の電気が流れるようになります。
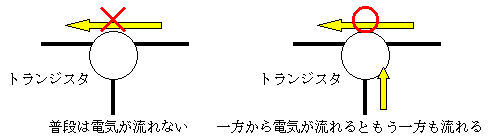
図4−1
トランジスタの役割は、スイッチの役割をしています。
ある条件で(ここでは、本当にスイッチを入れるという条件ですが)電気を流し、ある条件で電流を流さないようにするスイッチです。
(※余談ですが、この特性を生かして「トランジスタラジオ」は出来ています。高い電流を二方にかけておきます。そしてアンテナで受けた微弱な電波をもう一方から流します。そうするとその微弱な電波がスイッチの役割を果たし、高い電流が流れたり流れなかったりするので、最終的にアンテナで受けた電波を増幅しスピーカーから大きな音となって出力することが出来るのです)
トランジスタの中には、変わった奴もいて、先ほど説明したのと逆の動きをするものがいます。
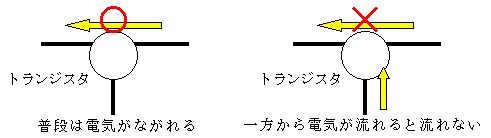
このトランジスタを図4につけると、普段は電気がついていて、スイッチを入れたら電気が消えるという、なんとも妙な動きになります。
ちょっと前までの章とは異なり専門的になってきましたが、まだそれほど複雑ではありません。
理解できますでしょうか?
ここまでが基本です。
本当に基本はこれだけなんです。
コンピュータはこれらの仕掛けを組み合わせて仕事をしています。
次の章からは、実際にどうやってこれらの仕掛けが計算など出来るのか話しを進めていきたいとおもいます。